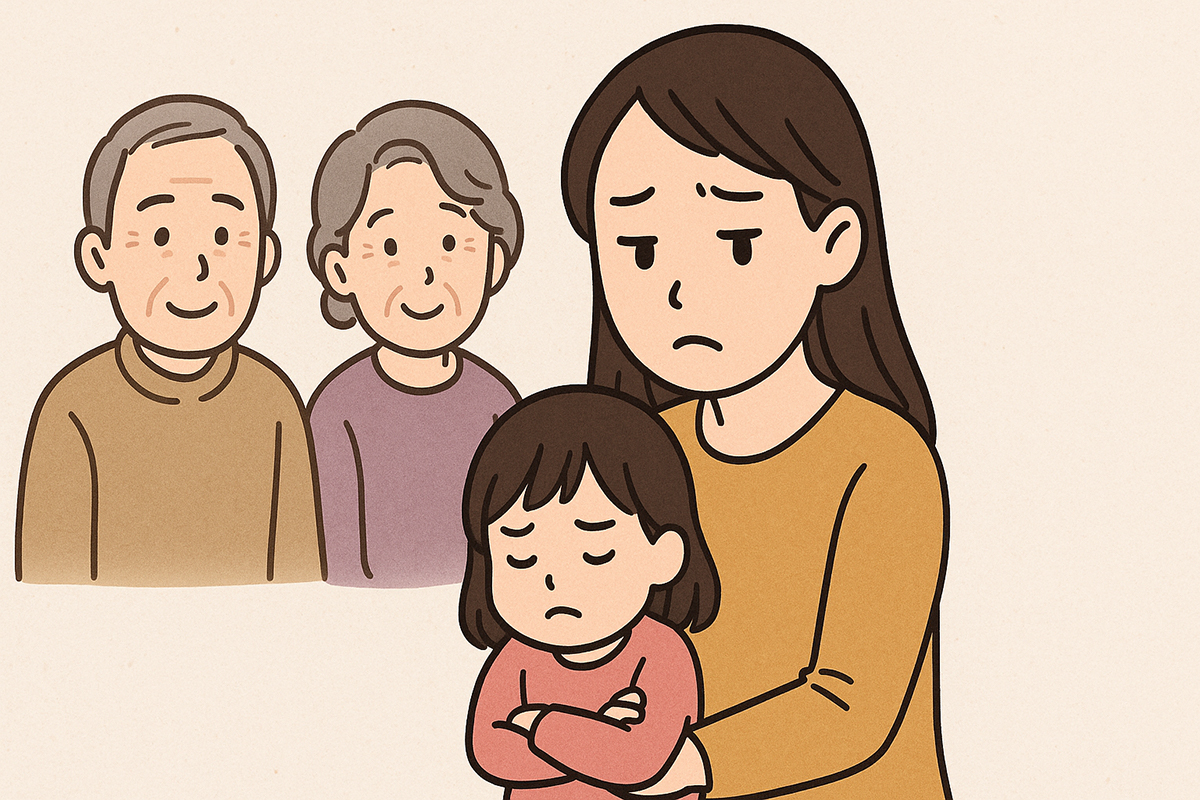「じいじ」「ばあば」が気持ち悪いのは、“老い”じゃなく“媚び”の匂いだ
呼称ににじむ“立場”ではなく“欲望”──誰のための「じいじ」か?
誰も言わないから、俺が言おう。
「じいじ」「ばあば」は、子どもが言いやすい言葉じゃない。大人が言わせたい言葉なんだよ。
「ばあばだよ〜」と自ら名乗る祖母。「じいじ、来たよ〜」と抱きかかえる祖父。
──その言葉に込められているのは、年長者としての誇りじゃない。孫に好かれたい一心の自己演出だ。
かつて「祖父母」とは、親よりも遠くて、でも親以上に“大きな何か”を象徴する存在だった。
今はどうだ? 呼び方一つで、孫の“お友達ごっこ”に参加してるだけじゃないか。
なぜ「じいじ」「ばあば」は気持ち悪いのか?
その違和感の正体、語感の問題じゃない。
「老いを認めたくない大人の、擬似的な若返り」による臭みだ。
「おじいちゃんなんて呼ばせたら、自分が年寄りみたいじゃん」「ばあばの方が可愛いから♪」
──誰のための可愛さだ?
「老いを肯定できないまま、子育てごっこを延長してる人」がいる。
その延長戦に子どもを巻き込み、「じいじ」「ばあば」と呼ばせてる。
つまりこれは“言葉のキャラ化”なんだよ。
キャラクターとして消費される老人像。
本来の“祖父母”という社会的な立場の骨格が消えた結果、ファンタジーだけが残った。
「おじいちゃん」「おばあちゃん」には、責任と重みがあった
「じいじ・ばあば」は軽い。
軽いからこそ都合がいい関係性を演じられる。
老いも威厳も要らない。ただ好かれる存在であればいい。
だが「おじいちゃん」「おばあちゃん」はそうじゃなかった。
敬語を学ぶ最初の相手。昔話の語り部。失敗を叱ってくれる大人。
──親でも先生でもない、けれど一線を引いて関わる存在。
「じいじ」「ばあば」と呼ばせることで、その一線は消える。
子どもと対等な存在になることで、教育の場からも降りてしまった。
家庭内フラット化がもたらす“規範の不在
「家庭なんだから自由でいいじゃない」「呼び方でモメるなんてナンセンス」
そういう声があるのは知ってる。
でも俺は言いたい。
“自由”ってのは、“ルールを守る力がある奴だけが持てる権利”だ。
家庭内で自由に呼び名を決めていい、というのは一見民主的。
だがそれは、秩序を教える機会を1つ失うということでもある。
社会に出れば、相手の年齢・役職・関係性に応じて言葉を変える必要がある。
そこを教える訓練場として家庭があるはずなのに、「ばあばがね~♪」「じいじがさ~」で全てがチャラになる。
呼び方がゆるければ、立場もゆるむ。
立場が曖昧になれば、誰も責任を取らない家庭になる。
結論──「じいじ」と呼ばせたいあなたは、“祖父”じゃない
これは老いの否認ではない。
“権威”からの逃避だ。
祖父母というのは、親の次に子を導く存在だ。
ときに違う価値観を伝え、ときに家族の外からの目線で子を見守る。
その「外」の立場こそが、家庭にとって大切な“間接照明”だった。
なのに今や、「じいじ」「ばあば」と呼ばれたがる人々は、その照明のスイッチを自ら消し、リングライト片手に孫と自撮りしてる。
最後に言葉は記号だ。でも、その記号が家族の構造を作る。
だからこそ、「じいじ」「ばあば」はただの愛称ではない。
家庭が“親と子の閉じた関係”から、“年齢と距離感を超えた多層構造”へと進化するための、通過儀礼のはずだった呼び名なのだ。
それを放棄するなら、家族というものは、ただの“好き合うグループ”に過ぎなくなる。
──それで本当にいいのか。
そう問い直す必要がある。
こんな記事もお勧め
「パパ・ママ」と呼ぶ大人たち――親離れできないまま年を重ねるという現実