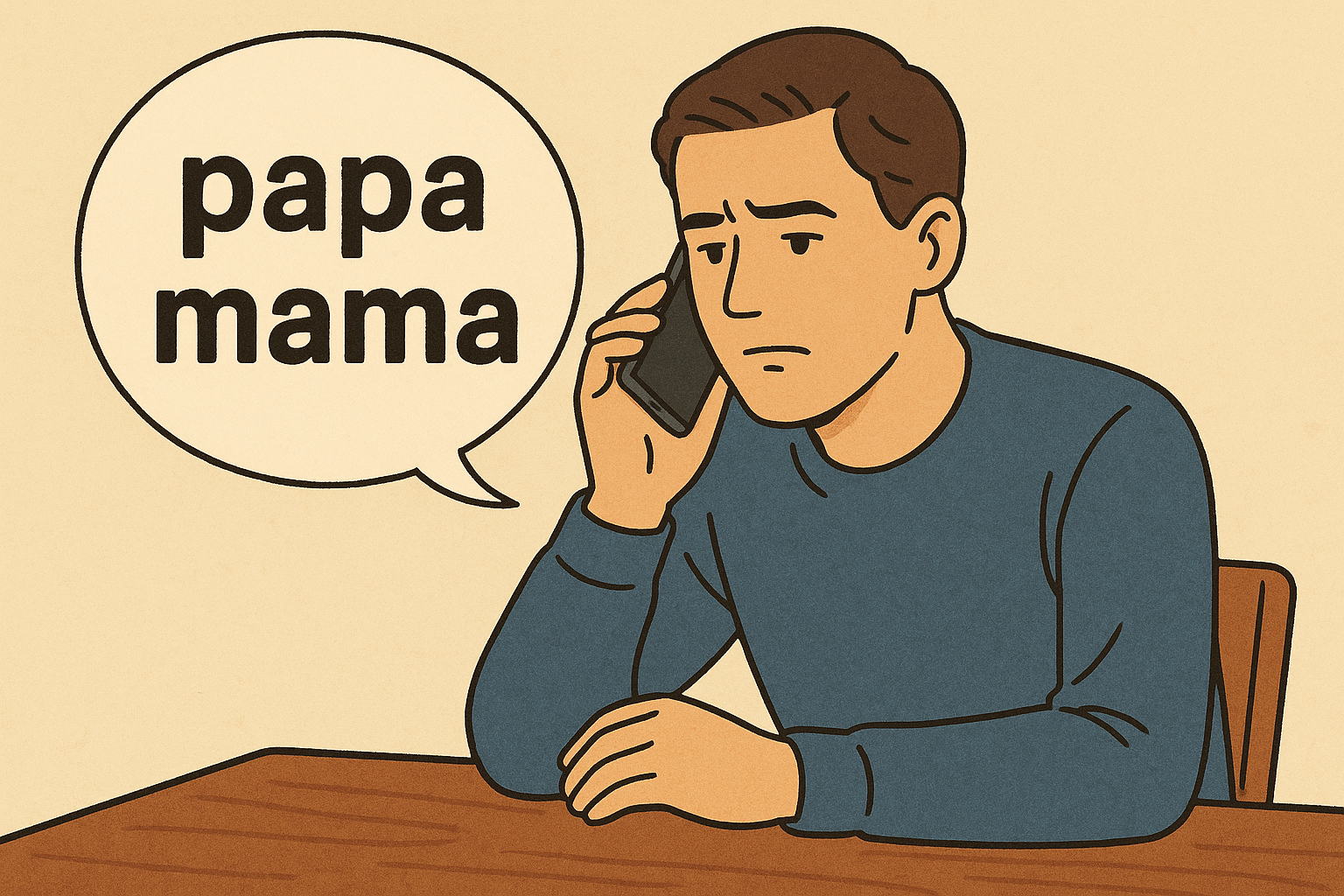「パパ・ママ」と呼び続ける大人たちへ――“親離れできない子どもたち”という観点から捉える家庭と社会の変質
あなたの周りにもいないだろうか?
いい歳をして「パパがね」「ママがさ」と言う人。
最初は軽く流していても、2度3度と聞くと、こう思うはずだ。
いつまで親を“子どもの目線”で呼び続けているんだろう?
その違和感は、場違いな軽さに由来するだけではない。
言葉というのは、習慣であると同時に“立場”を表現するシグナルでもある。
つまり「パパ」「ママ」と呼び続けることは、無意識にでも、自分の立ち位置を“子ども”に据え置いていることの表れなのだ。
その言葉が放っているのは、単なる甘えでも、家庭内のローカルルールでもない。
“大人になることを拒んでいる”というメッセージかもしれない。
そしてそれは、会話のテンポを乱す以上の影響を周囲に与えている。
言葉を交わす相手に、「あなたはまだ精神的に親離れしていないのでは?」という印象を与え、時には信頼や距離感にも微妙な歪みをもたらす。
多くの分析は、「親が老いを拒む姿勢」や「家族のフラット化」に原因を求めがちだ。
たしかに、親が“若くいたがる”文化が後押ししている面もあるだろう。
だが、それは半分しか見ていない。
むしろ問題の本質は、子ども側の“自立拒否”にある。
「大人として親と向き合うことを避けている」のだ。
その回避の手段として、「パパ・ママ」という呼称が利用されている。
私たちは、ただの呼び方の話をしているのではない。
言葉を通じて、家庭内の力学や、自分自身の成長を問い直す必要があるのだ。
「パパ・ママ」呼びに込められた“役割の固定化”
親を「パパ」「ママ」と呼び続けることには、構造的な意味がある。
それは、自分を永遠に“子ども”として位置づける行為だ。
- パパが心配してくれて〜
- ママがまたLINEしてきて〜
と語ることで、自分の立場を「まだ守られる側」に留めておける。
この構造は、意識的であれ無意識であれ、精神的な依存と未熟性を温存する仕組みだ。
しかもこの未熟性は、社会的な責任からの回避とも結びついている。
「パパ・ママ」の延長線上にあるのは、“まだ責任を取る側ではない”という自己定義。
年齢に応じて役割が変化するはずの家庭内で、その更新を拒む態度でもある。
家庭は“変化する劇場”であるべきだった
人は成長する。
子どもだった自分も、ある時点で「成人」となる。
本来、呼び名の変化はその通過儀礼だったはずだ。
- 父母(ちちはは)
- お父さん・お母さん
- 父・母
だが現代では、この移行が行われず、家庭という舞台が更新されないまま「子どもごっこ」が続いている。
かつて、呼び方の変化には、役割の自覚が伴っていた。
「父・母」と呼ぶようになった時、それは“親を人間として見る”という視点の獲得でもあった。
にもかかわらず、今やその通過儀礼が無効化されている。
家庭は“固定された関係性の演劇”を繰り返す場所と化してしまっている。
「父」「母」と呼べないということは?
「父」や「母」と呼ぶとき、人はある種の“距離”と“尊敬”を滲ませる。
それは、「対等な大人として向き合う覚悟」の表明でもある。
ところが「パパ・ママ呼び」に固執する大人は、
- 距離を取るのが怖い
- 親を“他人”として見られない
- 自分の変化を受け入れたくない
という状態にある。
これは、親の老いを否定するのではなく、自分の成長を否認する行為だ。
そしてこの否認は、しばしば“生活の延命”という形で表出する。
いつまでも実家暮らし、家事を任せきり、親に決断を委ねる。
こうした行動は、呼び方と連動していることが多い。
つまり、「パパ・ママ」と呼び続ける限り、精神的にも生活的にも“巣立ち”は起こらない。
社会にも波及する“呼称の未成熟”
呼び方は家庭の中だけに留まらない。
SNSや結婚式のスピーチでも、「パパ・ママ」呼びは広がっている。
- ママ、ありがとう。生んでくれて…
- 今日もパパとドライブ♪
それは親への感謝ではなく、「私はずっと可愛い子でいたい」という自己演出に過ぎないのではないか?
こうした“幼児化された言葉”が社会に持ち込まれると、
- 敬意の構造が崩れる
- 親と他人の区別が曖昧になる
- 年齢による立場の違いが認識されない
といった、言葉のインフレーションが起きる。
また、ビジネスシーンにおいても、“親しさ”と“軽さ”が混同されやすくなる。
人間関係の線引きが甘くなり、世代間の意思疎通にズレが生じやすくなるのだ。
「親のせいにするな」論を超えて
「親が可愛がられたいから」「ママと呼ばせたいから」そういう声も聞く。
だが、もしあなたが成人しているなら、もう親の責任ではない。
呼び方を変えるのは、あなた自身の“自立”の問題だ。
- 自分の親を「父」「母」と呼べるか?
- 他人に説明する時も、そう言えるか?
- 子としての役割を手放せるか?
これらは、人生の役割更新に直結している。
そして同時に、「自分の子どもには何と呼ばせるか」という問いも伴う。
親から受け取った呼び名を、自分の世代でどう扱うか。
呼び方の“継承”ではなく“再構成”が求められているのだ。
結論:「パパ・ママ」呼びは“未熟なアイデンティティ”の証明だ
「パパ・ママ」と呼ぶこと自体が悪いのではない。
問題は、それを更新できないこと。
その言葉にしがみつくことで、自分のアイデンティティが固定され、社会との間に微妙なズレが生まれる。
呼び名を変えることは、親子関係を“対等”にアップデートする手段だ。
大人になるとは、言葉を変えること。言葉を変えられる人が、役割も変えられる。
最後に問う。
あなたは、自分の親を「父」「母」と呼べるか?
それができないのなら、それは“あなたの問題”だ。